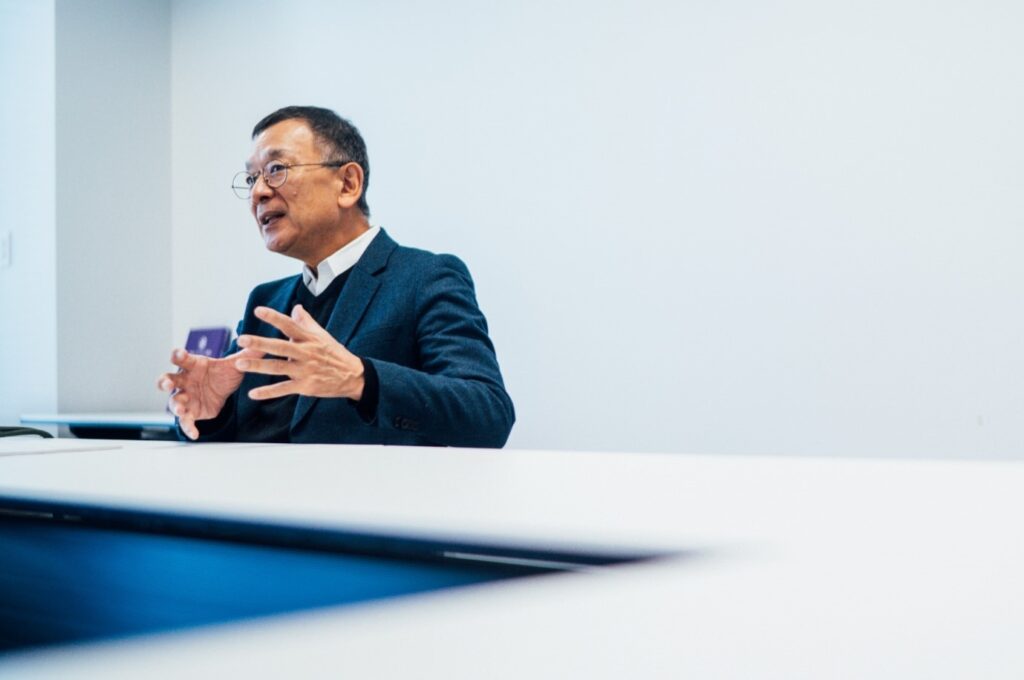クラブのオーナーや株主との関わりもあるのでしょうか。
ヴィッセル神戸やV・ファーレン長崎のようなオーナー型のクラブもあれば、数多くのステークホルダーに支えられる地域・市民型のクラブもあり、それぞれでオーナーシップの形態が全く違います。Jリーグにはプロ野球のオーナー会議のようなものはありませんが、必要に応じてコミュニケーションを取るようにしていました。
米国等の海外ではプロスポーツクラブも企業経営と同じように、クラブのバリューアップに多くの投資がなされ、クラブもファンもオーナーもWin-Winの関係を築くという考え方がありますが、日本ではまだビジネス投資の意識は米国ほど確立していません。私がチェアマンを退任する前にJクラブの上場を可能にしましたので、上場を目標に経営するクラブが現れ始めると、新しいステージが見えてくるでしょう。
Jリーグはバリューアップという考え方を持っているのでしょうか。また、その価値はどのような基準で測定するのでしょうか。
Jリーグは公益社団法人として税金が減免されており、収益は株主や役員に配当するのではなく、公益事業に再投資しなければなりません。ですから公益法人の価値は、公益性がどれだけ高まったかで測定する必要があります。一つの基準としては、リーグ全体の入場者数が挙げられます。どれだけの方々がJリーグに価値を感じてスタジアムに足を運んだかの結果だからです。
バリューアップの観点では、Jリーグとして「シャレン!(社会連携活動)」という言葉を提示し、社会に対する貢献価値を定義しました。各クラブはホームタウン内で小学校や病院を訪ねたり、地域の祭りに参加したりし、クラブのファンになってくださいという二者間取引で、その交換価値をベースにした社会活動を行っています。我々は、一つの社会課題をテーマに3社以上が協業した活動をシャレン!と定義し、その活動が社会にどのくらい広まっているかを指標にしました。
シャレン!は独特な施策だと思いますが、どういった経緯で始まったのでしょうか。
Jリーグ規約では、Jリーグに入会するクラブはホームタウンを定めなければならず、ホームタウン内で社会貢献活動を含む活動を行わなければならないと定義しています。Jリーグでは毎年その活動回数を計測していて、当時全50クラブの合計が延べ約20,000回、1クラブあたり年間400回という驚きの数字でした。
リーグとして地域密着を掲げ、クラブが一生懸命に取り組んできた結果ですし、私としてはこれ以上、活動回数を増やすのは無理だと思いました。クラブのリソースには限りがあり、ホームタウン活動自体が大きな収益をもたらすものではないからです。
そこで、「Jリーグが社会に貢献する」ではなく、「社会がJリーグを使う」と、主語を転換しようと考えました。理事だった米田(惠美)さんにコンセプトを伝え、最終的には彼女が仕立ててくれました。地域課題に対するソリューションを持っているのは、地域の企業や行政、市民ですから、彼らがJリーグというアセットを使ったら何ができるのかと、アイデアコンテストを実施したのです。
シャレン!によって、Jリーグにはなかったノウハウが数多く見えましたし、JリーグやJクラブの価値は、それらをつなぐハブになれることや情報発信力だと感じました。シャレン!の実践主体は各クラブですが、リーグとしてコンセプトを整理し、プラットフォーム化したことも補完する役割の一つだと思います。
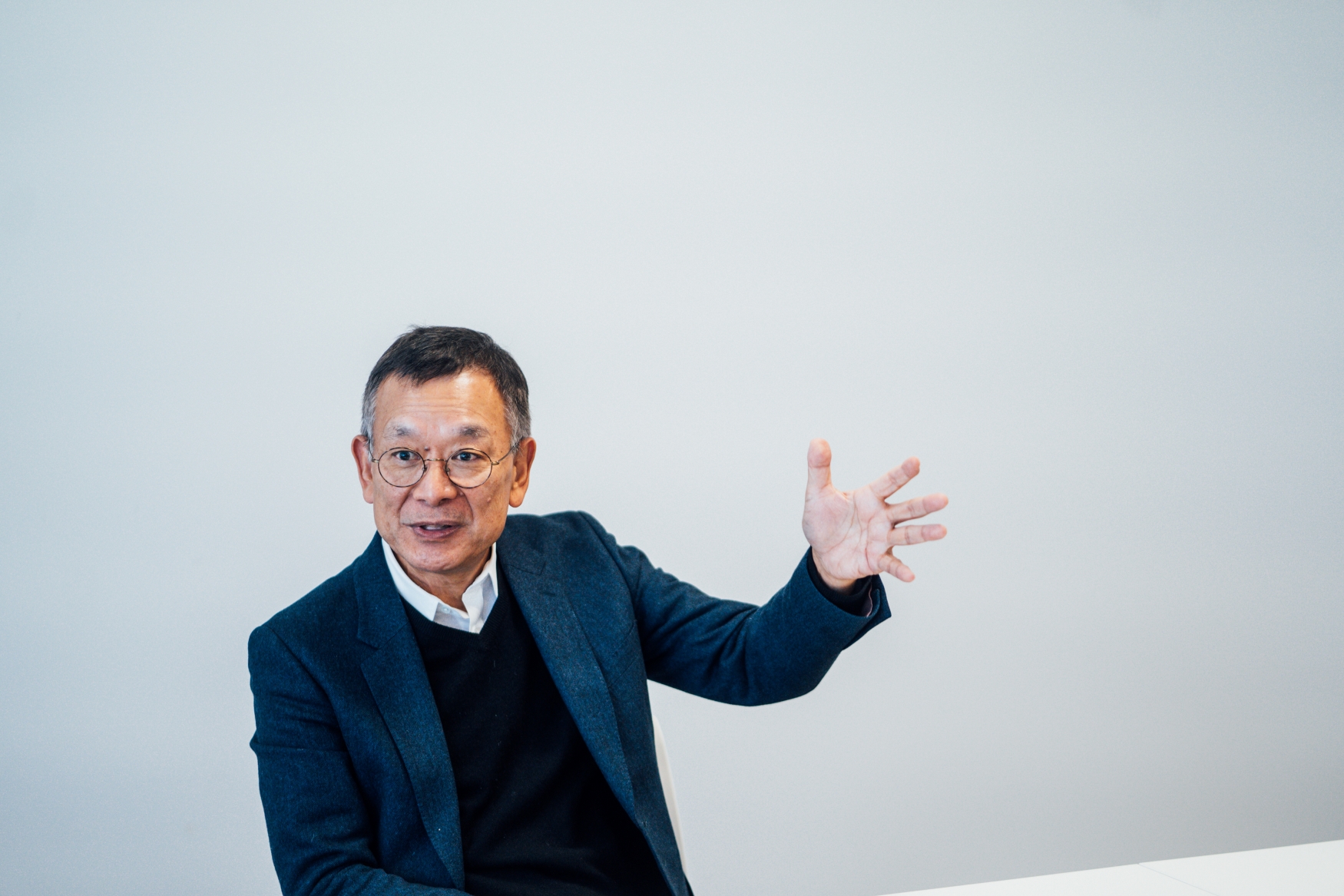
Jリーグの財務状況を改善するために何をされたのでしょうか。
ありとあらゆることをやらざるを得ない状況でした。プロモーションを行うにもお金をかけられないので、ファンエンゲージメントを高めるために最初に実施したのは、「チェアマンの3つの約束」という宣言を作り、すべての関係者にメッセージを送ったことです。
(1)笛が鳴るまで全力プレー(2)リスタートを速く(3)(時間稼ぎのような)見苦しい交代はやめてほしい、というものです。ファンの方々は貴重なお金でチケットを買ってくれているのですから、プレーに関係ない時間はできるだけ減らしましょうという意図です。サッカーの魅力を高めるために、資金を使わず、このような愚直な施策から始めました。
実際、2014年ブラジル・ワールドカップでコーナーキック、ゴールキックに要した時間を全て計測したところ、日本がコーナーキックを蹴るまでに30.6秒かけているのに対し、全試合平均は26.4秒で 4秒以上も早かったのです。その数字を同年のリーグ再開後から毎週開示し、今週は何秒だったと徹底して伝えた結果、段々と数値が改善していきました。民間企業の業務遂行と同じで、KPIをセットしてPDCAを回していくようなことを1年かけてやりました。
また、大きな出来事の一つに明治安田生命との契約が挙げられます。私がチェアマンに就任したときはJ3リーグのパートナーでしたが、2015年からはJ1からJ3までの全リーグのタイトルパートナーになっていただき、ようやく薄日が差してきました。コスト削減も徹底的に行いましたね。オフィスのスペースを約半分にして賃料を減らし、コロナ前から完全フリーアドレス化やリモートワークを導入していました。
DAZNとの契約は金額的にもインパクトが大きかったのではないでしょうか。
DAZNとの10年2,000億円の契約はコスト対策の象徴的な施策と見られがちで、これによって財務破綻を回避できたのは事実ですが、本質的な狙いはデジタルプラットフォームを構築し、リーグやクラブが試合動画を積極的に活用できる状態を整えることでした。
それ以前の放映権の考え方では、著作権は中継制作を行ったテレビ局側が保有していて、JリーグやJクラブが動画を使用する際には局側の許諾が必要で、かつ利用料を払う必要がありました。DAZNとの交渉の最重要ポイントは、映像のライツホルダーはJリーグであり、中継制作の主体者であるJリーグが著作権を持ち、DAZNには配信権だけを販売した点です。
結果として、試合の映像はJリーグが管理できるようになり、クラブはスピーディに動画を活用できるようになりました。数年でTwitterのインプレッション数は約30倍にはね上がり、Jリーグ全体のプロモーション活動に大きな変化が生まれました。

リーグとして、クラブ経営を具体的にサポートされたことはありますか。
実は、志半ばで終わった幻のプランがあります。コロナ以前にJ1全クラブの経営力を測定するアンケート調査を行いました。内容はサッカーと直接関係のない事柄で、「トップの意向が現場に伝わっているか」、「クラブのフィロソフィーを言えるか」など、クラブ内の価値観の浸透度合いを中心に、各クラブ内のスタッフや選手を対象に調査を行いました。
それに並行して、継続して勝点が増えている、または減っているかなど、競技力の推移を分析しました。経営力を縦軸に、競技力を横軸にして相関関係を見ると、経営力が高まっているクラブは競技力も安定して高まっていることが分かりました。一言で言うと、良い経営人材が集まっているクラブの未来は明るいということです。経営力と競技力の相関を科学し、現場で徹底することが重要だと考えていたのですが、コロナ禍の影響で検証をやり切れなかったのが残念です。
現在はバドミントン協会の会長でいらっしゃいますが、Jリーグで培ったものをインストールしていくお考えなのでしょうか。
バドミントンはサッカーとは全く違う世界です。チームスポーツであるサッカーで言えば、ファンはクラブにロイヤリティを持ちますが、個人競技の色彩が強いバドミントンではロイヤリティは個々の選手に向かいますし、その企業の社員としてプレーしている選手が多いため、企業スポーツの概念とプロのアスリートという意識の違いもあります。選手たちに紐づく形でファンの構造も全く違いますし、リーグやクラブの職員の立場や状況も異なります。
正直に言えば、ありとあらゆるものが違う状態に戸惑いながらも、バドミントンの発展に向けてどうしていけば良いかを考え、取り組んでいる日々です。Jリーグのやり方をそのまま導入してもうまくいかないでしょうし、アレンジの仕方が違うと考えており、これから様々な施策を検討、実行していきたいと思っています。間違いなくバドミントンは大きく発展するポテンシャルを持っています。
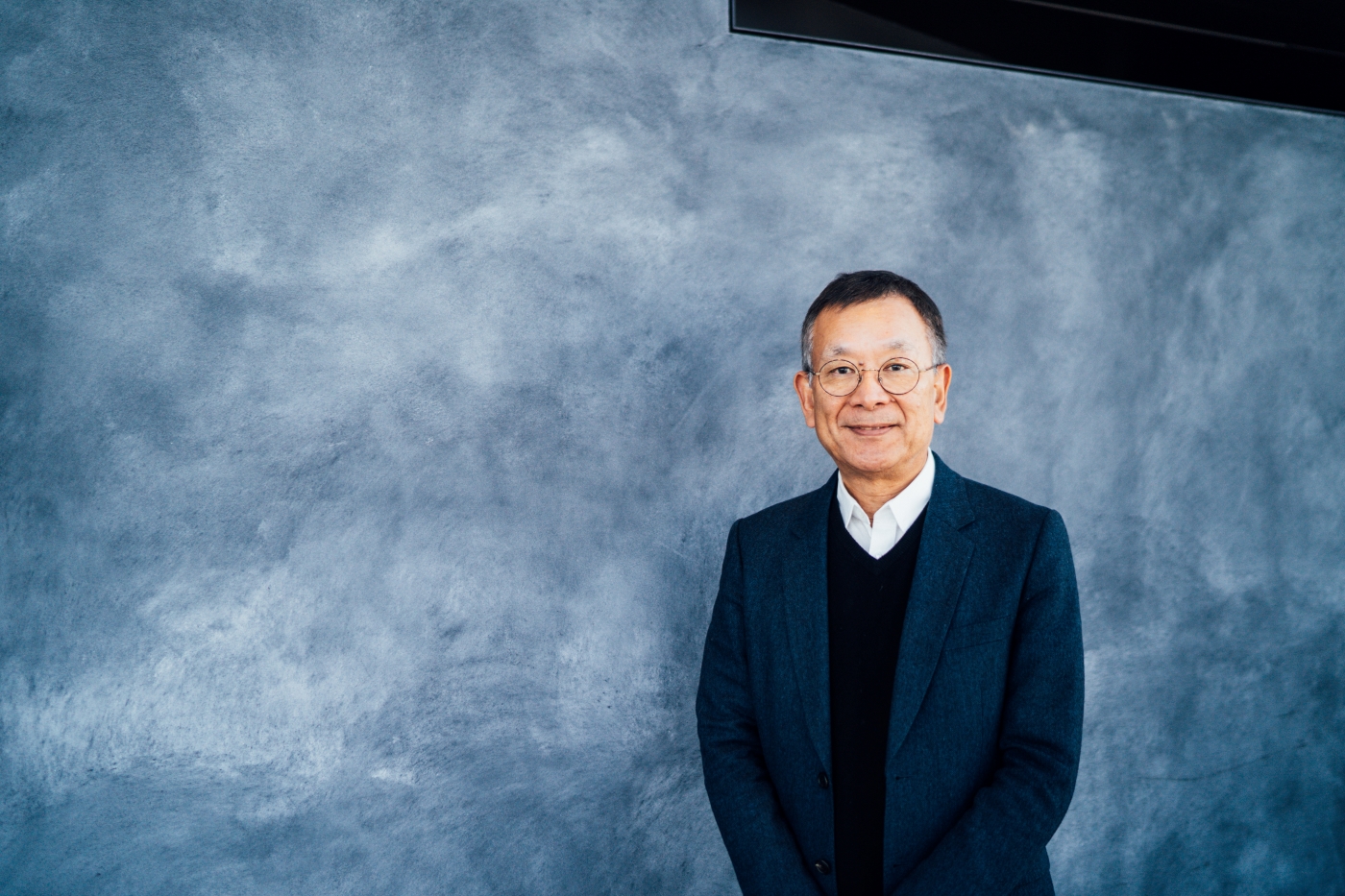
※前編(5/7掲載)は、こちら へ!